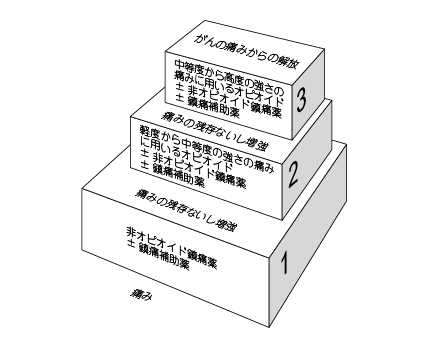3.WHO方式がん疼痛治療法
1.WHO 方式がん疼痛治療法とは
がん疼痛治療の成績向上を目指して作成された「WHO 方式がん疼痛治療法」を普及するために,「がんの痛みからの解放」の第1 版が1986 年に,そして第2 版が1996 年にWHO(世界保健機関)から出版された。
「WHO 方式がん疼痛治療法」が作成された意図は,全世界のあらゆる国に存在するがん患者を痛みから解放することである。これは,貧しい国でも,医療が十分に行き渡っていない国でも,痛みに苦しんでいるがん患者が存在するため,誰にでもできる疼痛治療法を普及させる,ということを意味する。その後,世界各国で翻訳されており,がん患者を痛みから解放することに貢献している。以下の記述は1996 年に発表されたWHO 方式に準拠する。
WHO 方式がん疼痛治療法とは,次の6 項目から構成される治療戦略であり,緩和ケアの中の一要素としてがんの痛みのマネジメントを実践すべきであるとされている。
- ① チームアプローチによる,がん患者の痛みの診断とマネジメントの重要性
- ② 詳細な問診,診察,画像診断などによる痛みの原因,部位,症状の十分な把握の必要性
- ③ 痛みの治療における患者の心理的,社会的およびスピリチュアルな側面への配慮と患者への説明の重要性
- ④ 症状や病態に応じた薬物または非薬物療法の選択
- ⑤ 段階的な治療目標の設定
- ⑥ 臨床薬理学に基づいた鎮痛薬の使用法
2.目標の設定
痛みのマネジメントで大切なことは,現実的かつ段階的な目標設定をすることである(表1)。第一の目標は,痛みに妨げられずに夜間の睡眠時間が確保できること,第二の目標は,日中の安静時に痛みがない状態で過ごせること,第三の目標は,起立時や体動時の痛みが消失することである。最終的にはこれらの目標を達成し,鎮痛効果の継続と平常の日常生活に近づけることが求められる。
しかし,骨転移の体動時痛を,動いても痛くないようにすることは難しい場合がある。また神経障害性疼痛の場合,症状の完全な緩和が困難な場合もある。これらのことを患者に理解してもらえるように,繰り返し丁寧に説明することが重要である。
| 第一目標 | 痛みに妨げられない夜間の睡眠 |
|---|---|
| 第二目標 | 安静時の痛みの消失 |
| 第三目標 | 体動時の痛みの消失 |
3.鎮痛薬の使用法
痛みの治療は薬物療法と非薬物療法の組み合わせが必要となるが,鎮痛薬(表2)の使用が主役となる。WHO 方式がん疼痛治療法における「鎮痛薬の使用法」は,治療にあたって守るべき「鎮痛薬使用の5 原則」(表3)と,痛みの強さによる鎮痛薬の選択ならびに鎮痛薬の段階的な使用法を示した「三段階除痛ラダー」(図1)から成り立っている。本項では以下に「鎮痛薬の使用法」について述べる。
なおWHO 方式がん疼痛治療法とは,非オピオイド鎮痛薬・オピオイドの使用に加え,鎮痛補助薬*,副作用対策,心理社会的支援などを包括的に用いた鎮痛法であり,薬物に抵抗性の痛みには,神経ブロックなどの薬物以外の鎮痛法を三段階除痛ラダーの適用と並行して検討すべきであるとしている。
*:鎮痛補助薬
主たる薬理作用には鎮痛作用を有しないが,鎮痛薬と併用することにより鎮痛効果を高め,特定の状況下で鎮痛効果を示す薬物(抗うつ薬,抗けいれん薬,NMDA 受容体拮抗薬など)。非オピオイド鎮痛薬やオピオイドだけでは痛みを軽減できない場合に選択される。参照。
| 薬剤群 | 代表薬 | 代替薬 |
|---|---|---|
非オピオイド鎮痛薬 |
アスピリン アセトアミノフェン イブプロフェン インドメタシン |
コリン・マグネシウム・トリサルチレートa) ジフルニサルa) ナプロキセン ジクロフェナク フルルビプロフェン※ 1 |
弱オピオイド |
コデイン | デキストロプロポキシフェンa) ジヒドロコデイン アヘン末 トラマドール |
強オピオイド |
モルヒネ | メサドンb) ヒドロモルフォンa) オキシコドン レボルファノールa) ペチジンc) ブプレノルフィンd) フェンタニル※ 2 |
- a :
- 日本では入手できない薬剤。
- b :
- 日本では経口剤のみ入手可能。
- c :
- がん疼痛での継続的な使用(反復投与)は推奨されていないが,他のオピオイドが入手できない国があるため,表に残された薬。
- d :
- 経口投与で著しく効果が減弱する薬。
- ※ 1:
- 原著では,基本薬リストに挙げられていないが,非オピオイド鎮痛薬の注射剤としてはフルルビプロフェンの注射剤(ロピオン®)がある。
- ※ 2:
- (強オピオイド)フェンタニルは,経皮吸収型製剤(貼付剤)と注射剤,経口腔粘膜吸収型製剤が使用できる。当時はフェンタニル貼付剤を使える国が限られていたことから,原著では基本薬リストに挙げずに文中での記載にとどめている。
〔WHO 編.がんの痛みからの解放,第2 版,金原出版,1996 より一部改変〕
|
❶ 経口的に(by mouth)
がんの痛みに使用する鎮痛薬は,簡便で,用量調節が容易で,安定した血中濃度が得られる経口投与とすることが最も望ましい。しかし,悪心や嘔吐,嚥下困難,消化管閉塞などのみられる患者には,直腸内投与(坐剤),持続皮下注,持続静注,経皮投与(貼付剤)などを検討する必要がある。
❷ 時刻を決めて規則正しく(by the clock)
痛みが持続性である時には,時刻を決めた一定の使用間隔で投与する。通常,がん疼痛は持続的であり,鎮痛薬の血中濃度が低下すると再び痛みが生じてくる。痛みが出てから鎮痛薬を投与する頓用方式は行うべきではない。
加えて,突出痛に対しては,レスキュー薬が必要になる。このため,鎮痛薬の定期投与と同時にレスキュー薬を設定し,患者に使用を促すことも重要である。
❸ 除痛ラダーにそって効力の順に(by the ladder)
鎮痛薬は,図1 に示した「WHO 三段階除痛ラダー」が示すところに従って選択する。ある鎮痛薬を増量しても効果が不十分な場合は,効果が一段強い鎮痛薬に切り替える。重要なことは,患者の予測される生命予後の長短にかかわらず,痛みの程度に応じて躊躇せずに必要な鎮痛薬を選択することである。またオピオイド使用時も,必要に応じて非オピオイド鎮痛薬や鎮痛補助薬を併用することが重要である。
- ① 軽度の痛みには,第一段階の非オピオイド鎮痛薬を使用する。これらの薬剤は,副作用と天井効果* 1 により標準投与量以上の増量は基本的には行わない。なお,痛みの種類によっては,第一段階から鎮痛補助薬を併用する。
- ② 非オピオイド鎮痛薬が十分な効果を上げない時,もしくは,軽度から中等度の強さの痛みの場合には,「軽度から中等度の強さの痛み」に用いるオピオイドを追加する。この段階でも必要により鎮痛補助薬の使用を検討する。
- ③ 第二段階で痛みの緩和が十分でない場合,もしくは,中等度から高度の強さの痛みの場合には,第三段階の薬剤に変更する。非オピオイド鎮痛薬は可能な限り併用する。それぞれのオピオイドの特性を理解したうえで薬剤の選択を行うことが重要であり,基本的には1 つの薬剤を選択する。モルヒネやフェンタニル,オキシコドン,メサドンなどの強オピオイドは,増量すれば,その分だけ鎮痛効果が高まる。第三段階でも必要により鎮痛補助薬の使用を検討する。
*1:天井効果(ceiling effect)
ある程度の量以上,投与量を増やしても鎮痛効果が頭打ちになること。有効限界ともいう。
❹ 患者ごとの個別的な量で(for the individual)
個々の患者の鎮痛薬の適量を求めるには効果判定を繰り返しつつ,調整していく必要がある。その際,非オピオイド鎮痛薬や弱オピオイドであるコデイン,トラマドールには天井効果があるとされる一方で,モルヒネ,オキシコドン,フェンタニル,メサドンなどの強オピオイドには標準投与量というものがないことを理解しておくことが重要である。適切なオピオイドの投与量とは,その量でその痛みが消え,眠気などの副作用が問題とならない量である。増量ごとに痛みが緩和すれば,その鎮痛薬を増量することで緩和できる可能性が大きい。レスキュー薬を使用しながら,十分な緩和が得られる定期投与量(1 日定期投与量とレスキュー薬1 回量)を決定する。
❺ その上で細かい配慮を(with attention to detail)
痛みの原因と鎮痛薬の作用機序についての情報を患者に十分に説明し協力を求める。時刻を決めて規則正しく鎮痛薬を用いることの大切さの説明と,予想される副作用と予防策についての説明はあらかじめ行われるべきである。
また,治療による患者の痛みの変化を観察し続けていくことが大切である。痛みが変化したり,異なる原因の痛みが出現してくる場合には,再度評価を行う。その上で,効果と副作用の評価と判定を頻回に行い,適宜,適切な鎮痛薬への変更や鎮痛補助薬の追加を考慮することが重要である。
がんの病変の治療(外科治療や放射線治療,化学療法など)によって痛みの原因病変が消失あるいは縮小した場合は,オピオイドの漸減を行う。神経ブロックなどにより痛みが急激に弱まった時は,投与量の急激な減量(もとの量の25%程度に減量)が必要な場合もある。その際には突然の中止は避け,離脱症候群*2 に注意したうえでの計画的な減量が必要である。
その他,患者の病態の把握は欠かすことができない。肝機能障害,腎機能障害のある場合は特に注意が必要である。高齢者はオピオイドの薬物動態が変化しているため少量からの開始が基本である。加えて,不安・抑うつなどの患者の精神状態に配慮していくことは,円滑な疼痛治療を行ううえで非常に重要である。
*2:離脱症候・離脱症候群
臨床では薬物の突然の休薬による身体症状を離脱症候群(withdrawal syndrome)と表現することが一般的である。退薬症状,退薬徴候ともいわれるが,本ガイドラインにおいては,ガイドラインを使用する医療従事者の混乱を避けるため,本文を通して離脱症候・離脱症候群に統一して使用する。
4.WHO 方式がん疼痛治療法の有効性と課題
WHO 方式がん疼痛治療法は,公表から25 年以上が経過しており,各国のフィールド調査で70〜80%以上の鎮痛効果が得られている。これは,オピオイドの定期投与,レスキュー薬による突出痛への対応,十分な副作用対策,適切な鎮痛補助薬の使用,および,患者教育などの複合的な支援が適切に行われれば,がん疼痛を緩和することが可能であることを示している。
一方,近年,WHO 方式がん疼痛治療法そのものは厳密な無作為化比較試験など科学的な検証を得たものではないことから,異なる枠組みの疼痛ガイドラインも提案されている。また,WHO 方式がん疼痛治療法に含まれる推奨のいくつか(除痛ラダー二段階目の必要性,経口投与の優先など)については,再検討が必要であるとする意見がある。
本ガイドラインでは,WHO 方式がん疼痛治療法は今後検証されるべき部分を含んではいるが,がん疼痛の緩和治療において指針となる重要な役割を有していると考える。
(長 美鈴,林 章敏)
【参考文献】
1) World Health Organization. Cancer Pain Relief, 2nd ed, World Health Organization, Geneva, 1996(世界保健機関 編.がんの痛みからの解放,第2 版,東京,金原出版,1996)
2) Ventafridda V, Tamburini M, Caraceni A, et al. A validation study of the WHO method for cancer pain relief. Cancer 1987;59:850-6
3) Mercadante S. Pain treatment and outcomes for patients with advanced cancer who receive follow-up care at home. Cancer 1999;8:1849-58
4) Azevedo São Leão Ferreira K, Kimura M, Jacobsen Teixeira M. The WHO analgesic ladder for cancer pain control, twenty years of use. How much pain relief does one get from using it? Support Care Cancer 2006;14:1086-93
5) National Comprehensive Cancer Network:NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Adult cancer pain.
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp
6) Eisenberg E, Marinangeli F, Birkhahn J et al. International Association for the Study of Pain. Time to modify the WHO analgesic ladder? Pain Clinical Updates 2005;13:1-4
<4.薬理学的知識>に続く